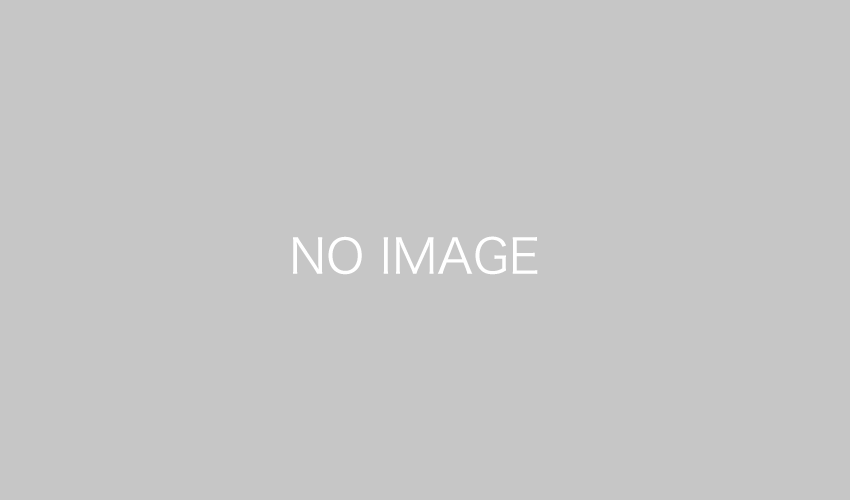よくある質問(FAQ)

状況によって最適な方法は異なるため、基礎知識から実務のポイントまでわかりやすく整理しました。
ここにない疑問や個別事情のご相談は、お気軽にお問い合わせください
A. 家族構成・財産の種類・お困りごと(相続人間の状況や期限の不安など)を中心に伺います。必要書類や次のステップもその場でご案内します。
A. 初回相談では特別な書類は不要です。家族構成や財産の概要をお話しいただければ十分です。正式にご依頼いただく際に、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書などをご準備いただきます。
A. 不動産や預貯金、株式などの資産のほか、借金などの負債も含まれます。プラス・マイナス両方を確認することが大切です。
A. 主な期限は「相続放棄が3か月以内」「相続税申告が10か月以内」です。その他の手続きにも期限があるため、早めの着手がおすすめです。
A. 例えば、自作の遺言書では法的要件を満たさず無効となるリスクがあります。専門家に依頼することで、法的に確実に有効な遺言書を作成でき、将来のトラブルを確実に防げます。また、最適な相続対策についてもアドバイスを受けることができます。
A. 遺言書がない場合、財産は法定相続分に従って分割されます。これによりご家族の意向と異なる分割となったり、相続人間でのトラブルが発生する可能性があります。遺言書があることで、あなたの意思を明確に示し、家族の平和を守ることができます。
A. はい、遺言書は何度でも書き直すことができます。新しく作成した遺言書が有効となり、古い遺言書は無効となります。当事務所では、内容変更時のサポートも承っております。
A. 自筆証書遺言の場合は法務局での保管制度を利用することをお勧めしています。公正証書遺言の場合は公証役場で原本が保管されるため安全です。保管方法についても詳しくご案内いたします。
A. 公正証書遺言は公証人が作成するため法的確実性が高く、原本が公証役場で保管されるため紛失の心配がありません。自筆証書遺言は費用を抑えられますが、要件を満たさないと無効となるリスクがあります。
A. はい、可能です。遺言書の作成は個人の意思によるものですので、ご家族に知らせる必要はありません。ただし、相続時に混乱を避けるため、信頼できる方に保管場所をお知らせしておくことをお勧めします。
A. 認知症などで判断能力が低下した場合、遺言書の作成は困難になります。そのため、元気なうちに遺言書を作成しておくことが重要です。将来の備えとして成年後見制度についてもご案内できます。
A. 遺言書がある場合は、原則としてその内容に沿って相続が行われます。遺言書がない場合は、法定相続分に従って分ける必要があります。